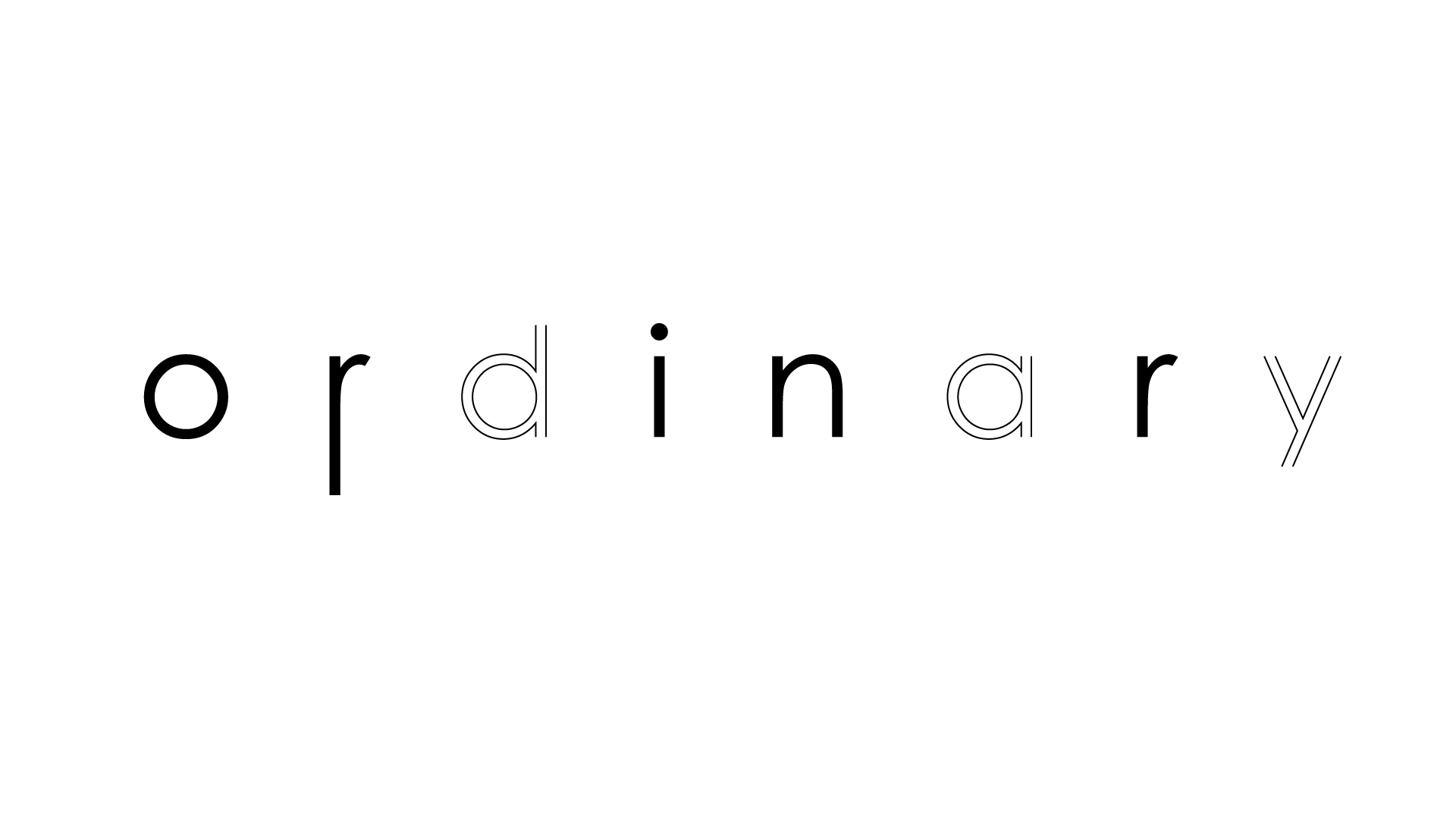シリーズ『青紗の本棚』は、作家/ライターの田中青紗(たなかあさ)が、自身の本棚から選んだ一冊をもとに広がる思考や体験を綴ったエッセイです。つい本棚に手を伸ばしたくなる不思議な体験をあなたに。 月2回更新予定。
毎週水曜日の夜になると、母はダイニングテーブルの上にカタログを広げていた。
子どもの頃我が家では、週1回の食材宅配サービスを利用していて、木曜日の夕方がお届け日。食材の受け渡しと一緒に次週配達してもらう分も注文するため、水曜日の夜はいつも購入品を用紙に記入する習慣があった。
「青紗、明日なんやけど宅配受け取ってくれん?」
とある水曜日の夜。母の言葉に当時小学5年生だった私は「えー」と声を漏らした。いつもは母が受け取っているが、明日は都合が悪いらしい。母が忙しいとき、私はときどき受け取りに出かける。
私が不満を口に出したのは、“受け取ること”が嫌だったからじゃない。受け取るためにご近所さんが集まる場に行くのが嫌だったからだ。
私の住んでいた地区では同じように食材宅配サービスを使う家庭が多かった。当時は地区の特性上、一家庭ごとに届けられるのではなく、ある程度の家庭分はまとめられて一箇所(家から歩いてすぐの場所)に配達される仕組みだった。決まった曜日、時間になると各家庭の代表が注文した商品を受け取りに行くシステムである。
ただパッと受け取ってパッと帰ればいいだけの話なのに。
ご近所さんだもん。子どもが受け取りに行くと、どうしたって話しかけられる。当時(今思うとおそらく)思春期を迎えていた私は、あれこれ聞かれるのが苦手になっていた。みんな優しい人ばかりなのにいつも緊張し、当たり障りない受け答えをしてそそくさと逃げ帰っていた。
冷蔵庫に届いた食材を入れる。だんだんと心が落ち着いてくる。こんなことで嫌だと思うなんて。毎回毎回愛想のない子どもだと思われていないだろうか。なんて考えて少しもやもすることが多かった。
母はまだ帰ってこない。姉は部活だし、弟はどこかへ遊びに行っている。まだスマホなんてない時代。テレビをなんとなくつけて、消して、やることがなくて、今週届いたカタログを見てみようと封を切る。食品ページをパラパラとめくり、カレンダーや書籍が特集されているページを見ていたときに、見覚えのある文字が飛び込んできて心が踊った。
*
「それ、面白い?」
学校の休み時間。声をかけると、同級生のNちゃんはページをめくる手を止めて顔を上げた。
「これ?面白いで!」
私に表紙を見せてくれる。『ダレン・シャン』と書かれているそのカバーには、リアルなロウソクやバラが描かれていて、少し不気味な印象を受けた。今三巻を読んでいると言う。
どんな話なのか聞いてみると、イギリスで生まれた大人気のファンタジーで、バンパイアにまつわる物語らしい。
読書好きな叔母の影響でもともと本はよく読んでいた。当時『ハリー・ポッター』を読んでいたこともあり、魔法とはまた違ったファンタジーに俄然興味が湧いた。「すごく面白いよ!」とおすすめしてくれるNちゃんは、とても楽しそうだ。たった数分程度のやりとりだったが、不思議と私は猛烈に「この本を読んでみたい」と思った。
チャイムが鳴る。不気味な雰囲気の表紙を頭の中で思い浮かべながら「今度本屋に行ったら探してみよう」と決意する。忘れないように「ダレン・シャン、ダレン・シャン」と口の中でタイトルを転がす日々が続いていた。
そんな矢先だったのだ。
カタログに掲載されている『ダレン・シャン』の一巻を見つけたのは。
いつもならすぐにタイトルを忘れてしまったり興味が薄れてしまったりすることも多かったけれど、『ダレン・シャン』だけはなぜか記憶に残っていて、「読まなければ」と私を突き動かすような感覚があった。
帰宅した母に「この本を注文してほしい」とお願いする。お年玉の残りで買うことを説明して、一緒に注文番号を確認しながら用紙に記入していく。初めて木曜日の配達が楽しみに思えた瞬間だった。
*

届いたダレンシャンは、私に知らない世界をたくさん教えてくれた。バンパイアのこと、先が読めない展開の面白さについて、今当たり前にある幸せ、家族、友達、仲間、強さ、愛、そして自分のこと。
私は夢中になって読んでいた。新刊が発売されるたびに本屋に行き購入する。ソファの上で一日中読んでいて、家族から呆れられることもあった。外伝も買ったし、作者のダレン・シャン先生のサイン会にも足を運んだ。
これまでさまざまな本を読んできたけれど「本って面白い」「私は読書が好きなんだ」とはっきり自覚できたのは、『ダレン・シャン』シリーズのおかげなのだ。
なぜこれほどまでにハマったのか。大人になった今でもふと、『ダレン・シャン』が心に残る一冊である理由を考えてみるけれど、こればかりは「縁」だったとしか言いようがない。
そんな本に子どもの頃に出会えたことは、何よりも私の財産になっている。
*
ダークファンタジーから始まった私の読書は、さまざまな作者やジャンルへと幅を広げていく。いつしかそれらは、文章を通じて私を安心させてくれる存在となった。
十代の頃、未熟ながらに感じていた田舎の閉塞感も、グループに属さないといけない違和感も、「こんなことをいちいち考えてしまう私は性格が悪いんじゃないだろうか」なんて思う自己嫌悪の夜も、自分に対する羞恥心も。読書をすることで「この気持ちは私だけじゃなかったんだ」と共感し安堵できた。
私にとって本とは、安心を与えてくれるものなのだ。
どうしたって生きていると、ささくれが生まれる。私は健康だし、幸せだし、何かがあるわけでもない。しかし誰かに話すほどでもない小さなささくれたちが、日々生まれていく。このささくれを癒してくれる心強い相棒が、私には必要なのである。
「私だけじゃない」というささやかな安心は、世の中をサバイブする中で拠り所となる。拠り所があるだけで、少しだけ息がしやすくなるのではないだろうか。大人になった今でも、私は安心を探して日々ページをめくっている。
あのときカタログをめくっていなかったら、どうなっていたのだろう。本を好きになっていなかったのかもしれないし、もっと偏屈な人間になっていたかもしれない。
あなたにとって、本とはなんだろう。